打合せも申請関係も大詰めとなり、いよいよ着工目前!
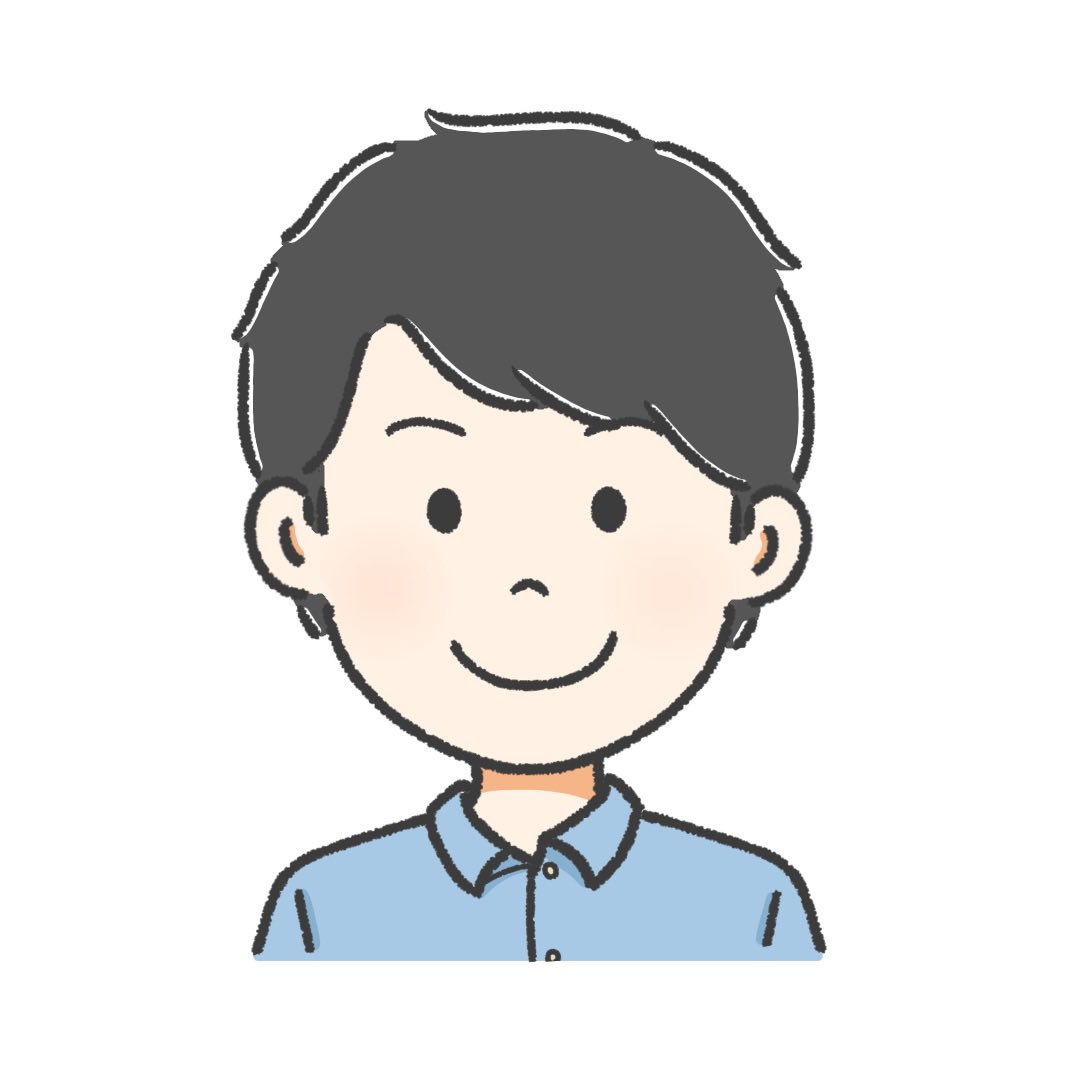 担当者
担当者地鎮祭の日取りを決めましょう
ということで、宮司さんと調整して予約(仮)
実家の母に地鎮祭の日程を伝えたら…
っていうかウチ喪中よ。やって大丈夫なの?
とまさかの展開。



そうだった!ウチは喪中だったんだ…
こんな時、神事である地鎮祭はどうするのか、確認しました。
喪中でも地鎮祭はできる!わが家は条件クリアしてました
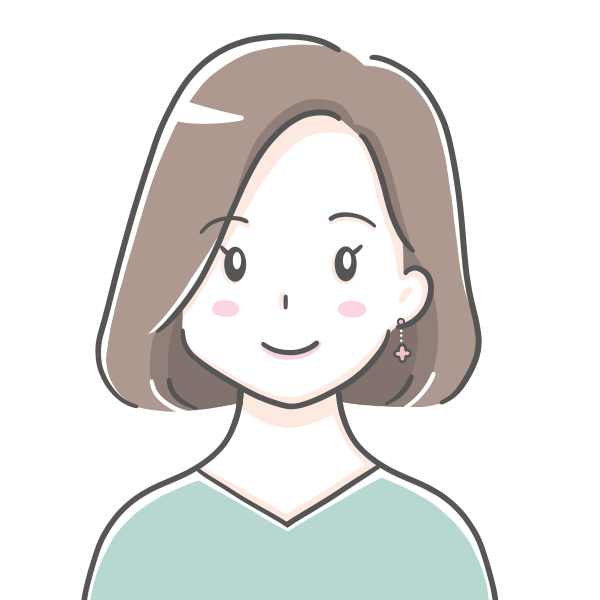
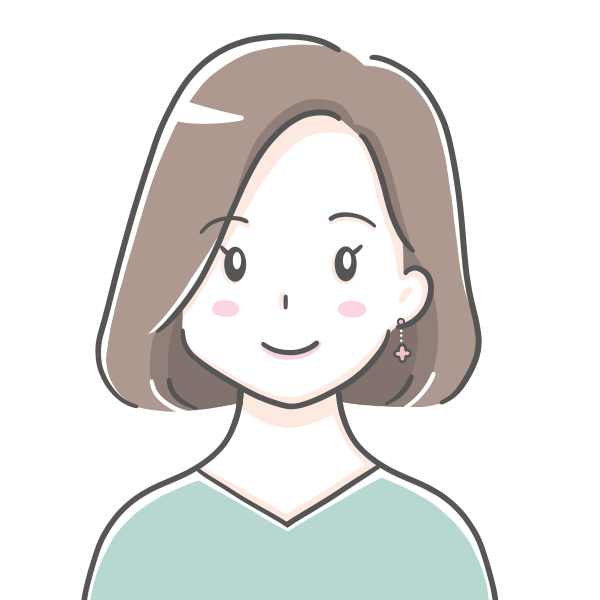
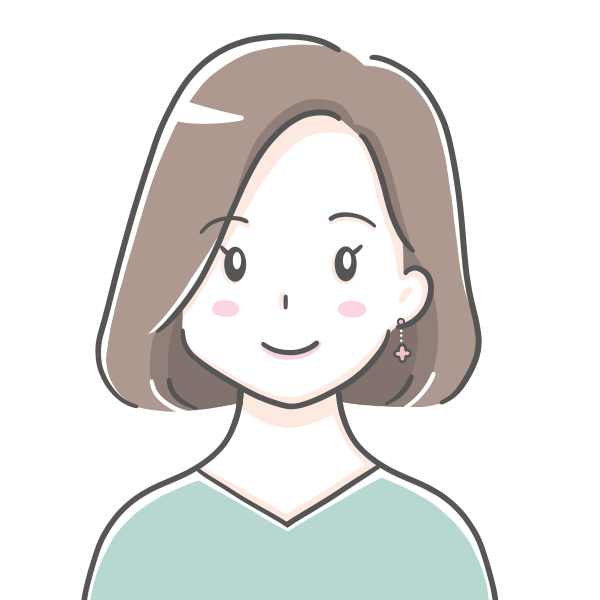
結論から言うと、地鎮祭できました。
担当さん→宮司さんに確認を取ってもらったところ…
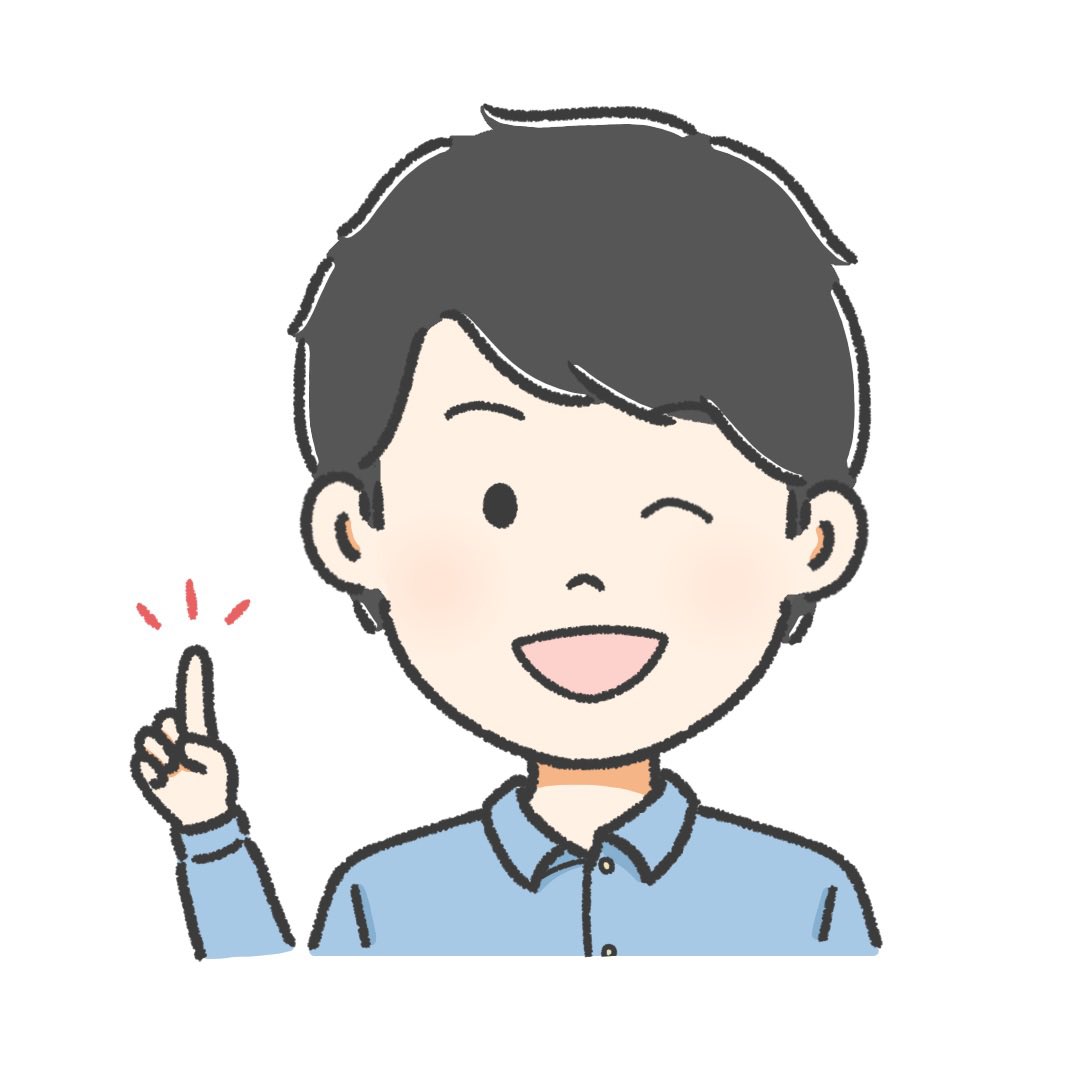
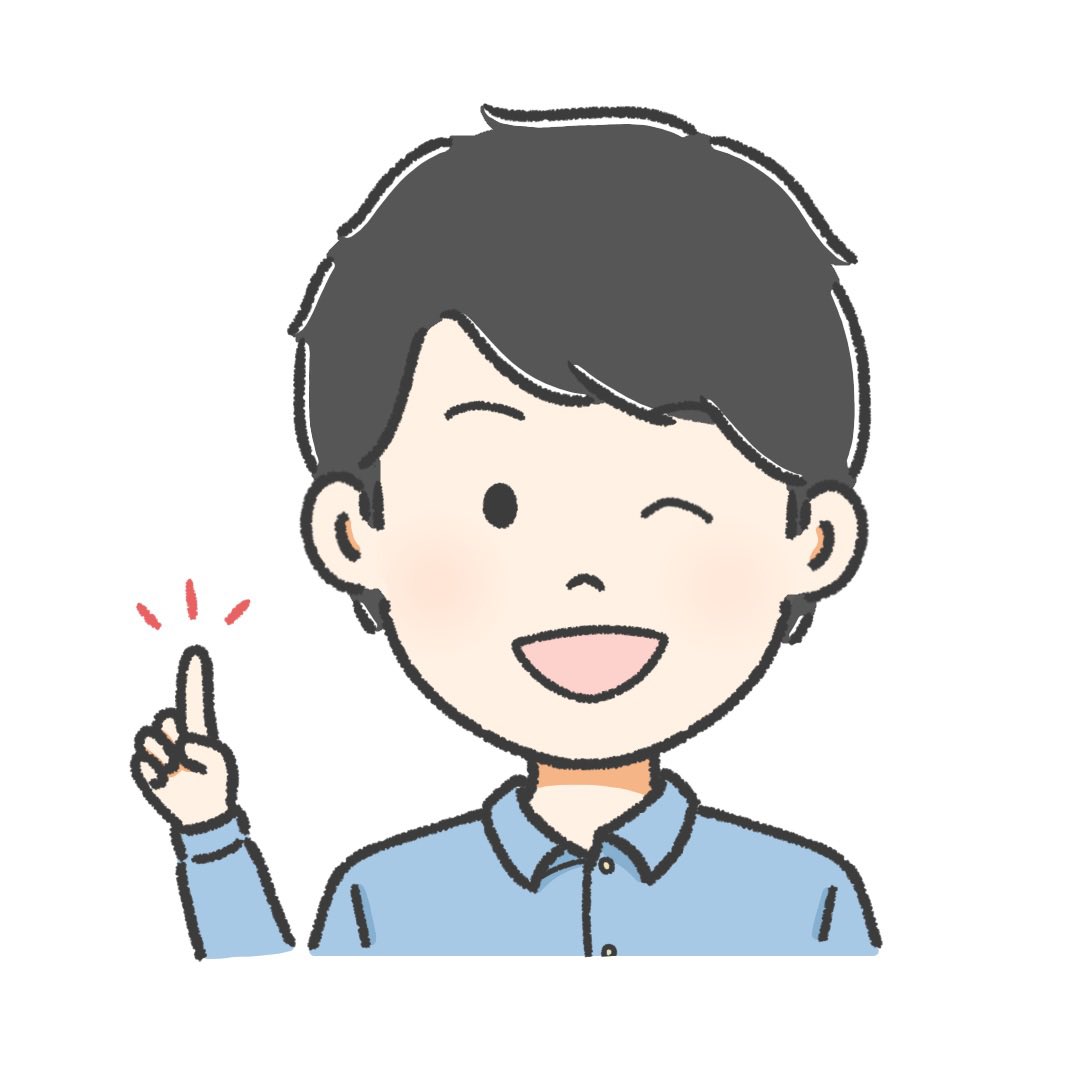
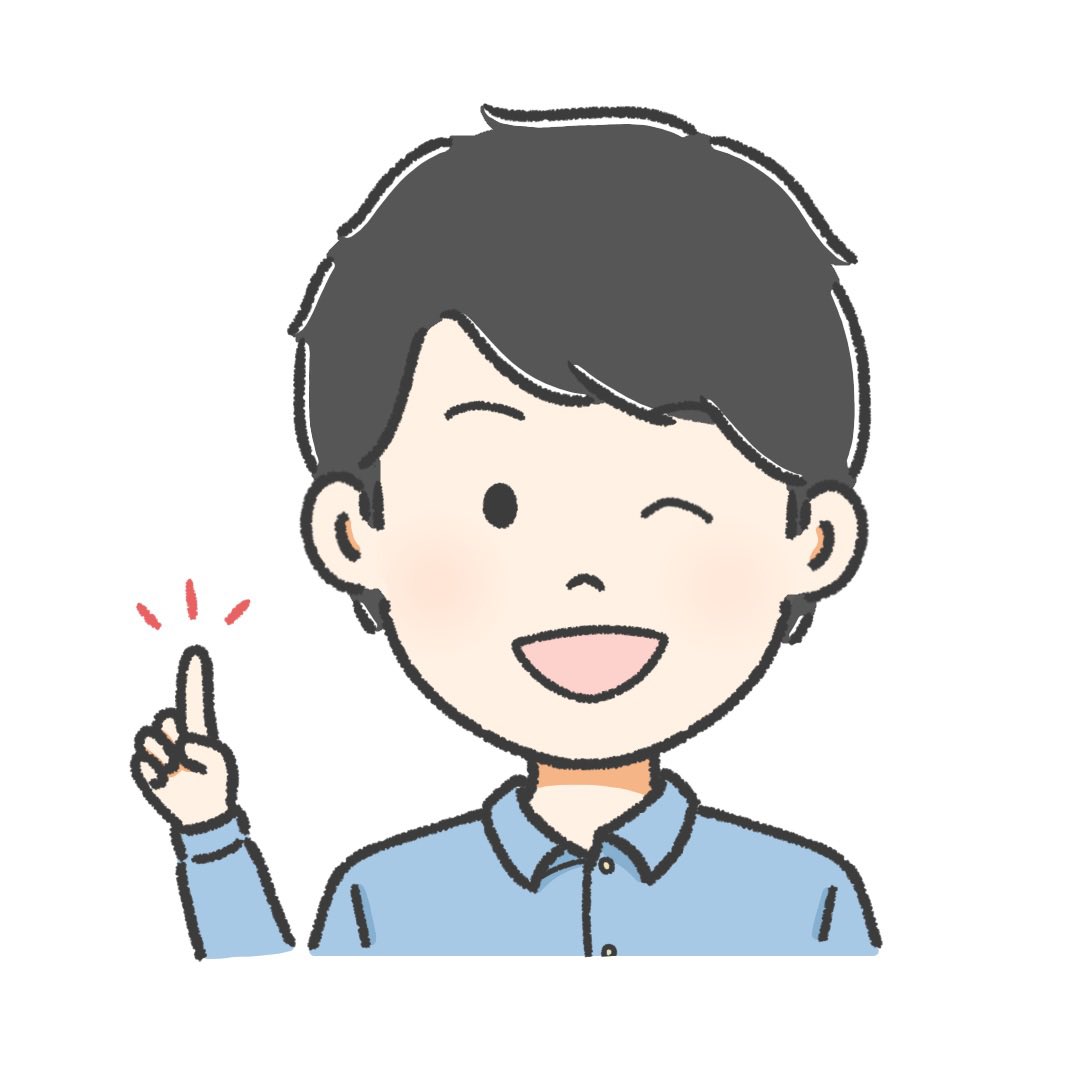
50日経っていれば問題ないそうです
とのことでした。
四十九日法要が済んで(神式では50日祭)忌明けされていれば特に問題はないようです。
参考までに…
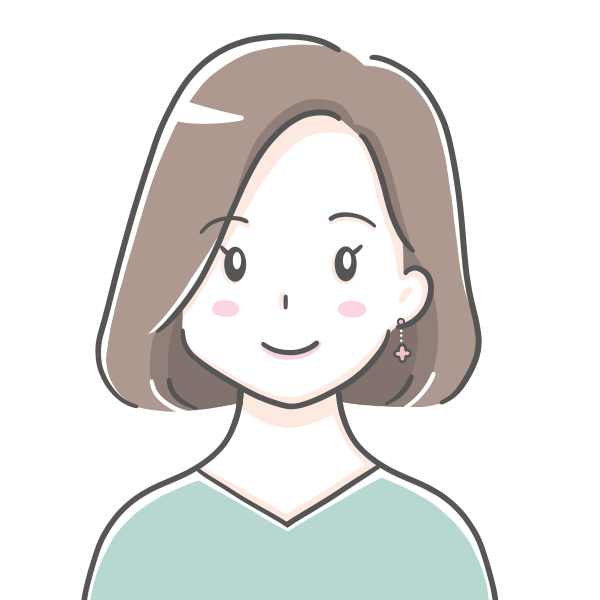
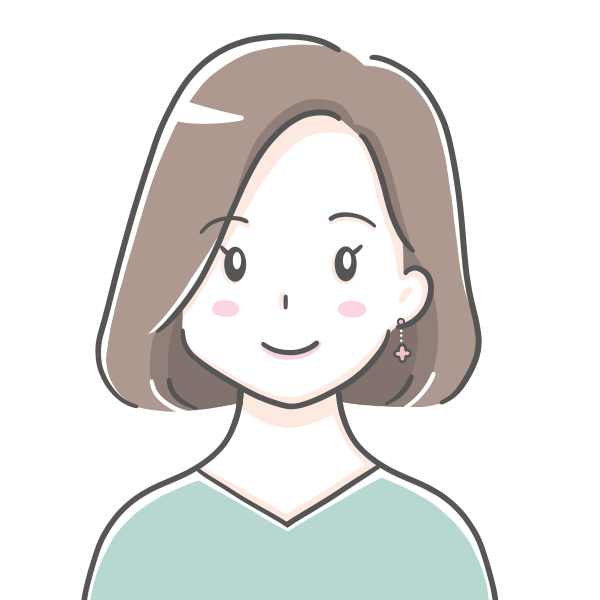
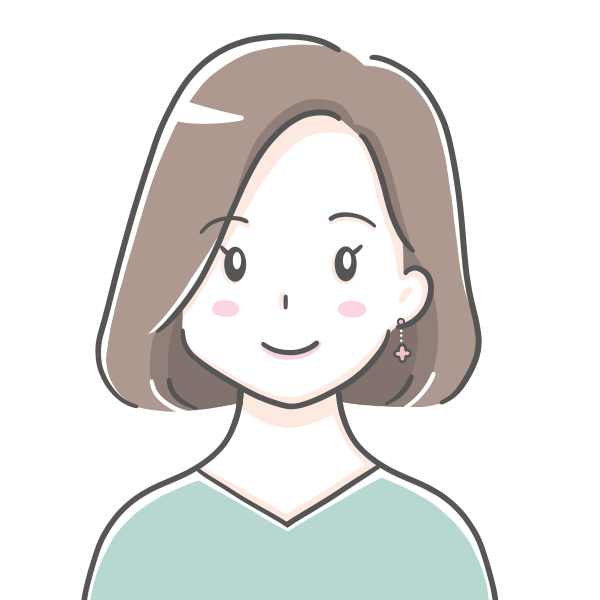
もしマイホーム計画中に身内に不幸があった場合は担当者さんや宮司さんにご確認くださいね
ご近所への着工前挨拶に持って行ったもの
確認ができて安心し、予定通り地鎮祭を執り行えることとなりました。
地鎮祭が始まる少し前にご近所への着工前挨拶をしてきました。
持参したのは、こちら



のし上は「御挨拶」で用意しました
プラス、ペットボトルのお茶を数本紙袋に入れました。
ご近所さんはご高齢な方が多かったので無難なものを選びました。
わが家の場合、実際の着工はしばらく後の予定だったのですがなかなか来れないこともあり早めに済ませました。
工事が始まる前に工務店からも挨拶しに行ってくださったようです。
地鎮祭の流れや用意するものは?夏場は暑さとの闘い!尾頭付の鯛はどうする?!
- 工事の安全を祈願する
- 土地を守っている神様に土地を使う許可をもらう
- その土地で暮らす人の繁栄を祈る
わが家の場合は、工務店の提携している宮司さんへお願いして設営からお供物まで全て準備して頂きました。


- 奉献酒
- お米
- お塩
- 野菜
- お魚(尾頭つきの鯛)
- 昆布やひじき等の乾物
- 水
- 果物
- 榊(さかき)
- 玉串料(初穂料)
1は工務店さんが用意してくださいました。
2〜9は宮司さんがご用意。
施主は10の初穂料を用意するだけでした。
玉串料(初穂料)は、3万円を用意するよう担当者さんに伝えられていたので、指示通り3万円をのし袋に入れて用意しました。
のし袋チェックポイント
- お祝い用
- 水引は紅白で蝶結びである
- 水引が取り外せて中袋が付いているもの
地鎮祭の所要時間は1時間ほどでした
地鎮祭の流れは以下の通り。所要時間は1時間ほどでした。
参列者やお供物を祓い清める儀式
その土地の神を迎える儀式
祭壇のお供え物を神に食べていただく儀式
工事の安全と家の繁栄祈願の祝詞を奏上する
土地の四隅をお祓い清める


小さく四角い紙を土地の四方に撒いてお祓い清めて頂きました。
宮司さまから施主が鍬を受け取り、神壇の前に用意されている盛り砂を「えいっ!えいっ!えいっ!」という掛け声と共に、三度掘る仕草をします


子供たちもやらせて頂きました。
その後、施工業者の番になり、担当者さんも。
慣れているので、声量がハンパなかった(笑)
神前に玉串を奉り拝礼
玉串を受け取り、神前の玉串台に供え、二拝・二拍手・一拝して自席に戻ります。
子供たちは七五三以来なので全然わけわからずやってましたが、きちんとできていました。
酒と水の蓋を閉じお供え物を下げる
神をもとの御座所にお送りする儀式
供え物のお神酒をいただく
子供はお水を用意して頂きました。コロナ禍ということで口はつけず形だけで終わりました。
以上、10工程ほどの儀式がありました。
終了後に御札を頂きました。引き渡し後に神棚に…とのことでした。
担当者さんにも紙製の御札を渡していて、着工時実際土地をいじる時に埋めていただく物だそうです。
お供えした奉献酒・鯛・野菜・果物・乾物もいただき、召し上がるまでが地鎮祭ということだそうです。
尾頭付鯛は鯛めしにして戴きました
持って帰ってきたお供物の中で一番大変だったのが、鯛です(苦笑)
とっても立派な鯛を仕入れてくださいましたw


夏場ということもあり、安全を考慮して「加熱して」頂きます。
我が家には魚を捌く用の包丁はないので、処理が簡単に済む鯛めしにしてみました。
- 鱗取りはペットボトルのフタが使える!
- 三徳包丁は刃が立たないのでキッチン鋏で捌く
鱗取りなんぞ持ち合わせていなかったのでどうしようかなぁと思ったのですが、ペットボトルのフタが使えました◎
鱗が生えてる逆向きにガガッと削いでいく感じでキレイに取れるのです!
内側のギザギザとフタのしなやかさで鱗をしっかりホールドしてる感覚。必死すぎて写真はないm(_ _)m
わが家の包丁はグローバルの三徳包丁なのですが、グローバルといえど、鯛の身は切れなかった…。
ハサミを使ってみたら、サクサク切れたので内臓の処理もスムーズにいきました◎
その調子で頭も切り落とし、しばらく料理酒につけておきました。
鯛を捌く前に米は研いで土鍋に準備をしておくとスムーズ。
調味料と鯛を入れて気づく。





尾がはみ出てしまう…
ちょっと折り曲げた状態で蓋をしました(苦笑)
詳しい作り方はクラシルのレシピを参考にしたよ〜
悪戦苦闘しましたが、とーっても美味しく炊けました!




暑い中バタバタした地鎮祭となりましたが、無事執り行うことができて一安心です。
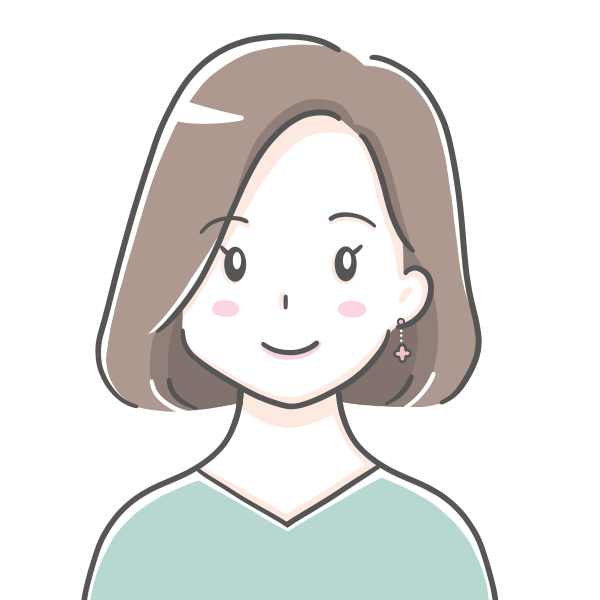
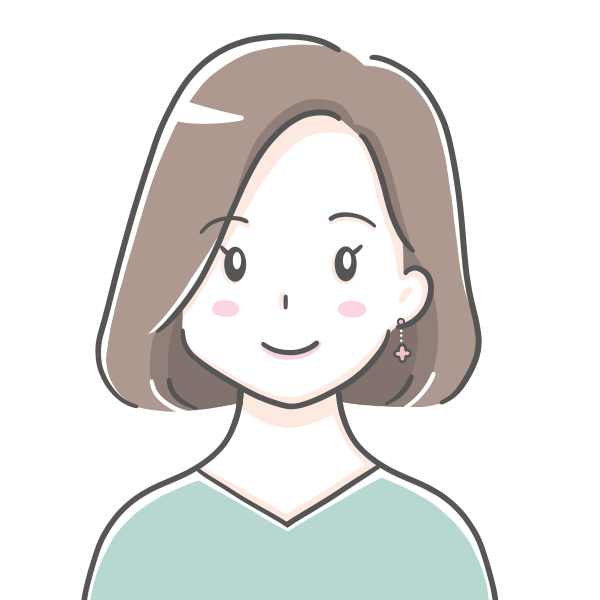
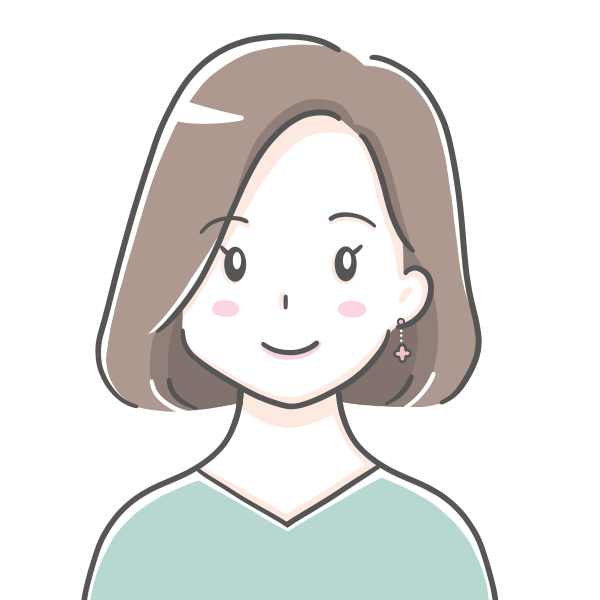
この調子で工事も安全に順調に進んで欲しいなと願うまでです。
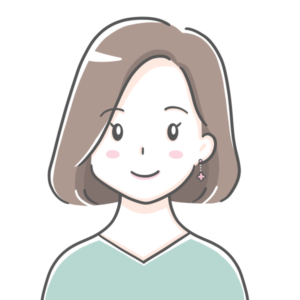
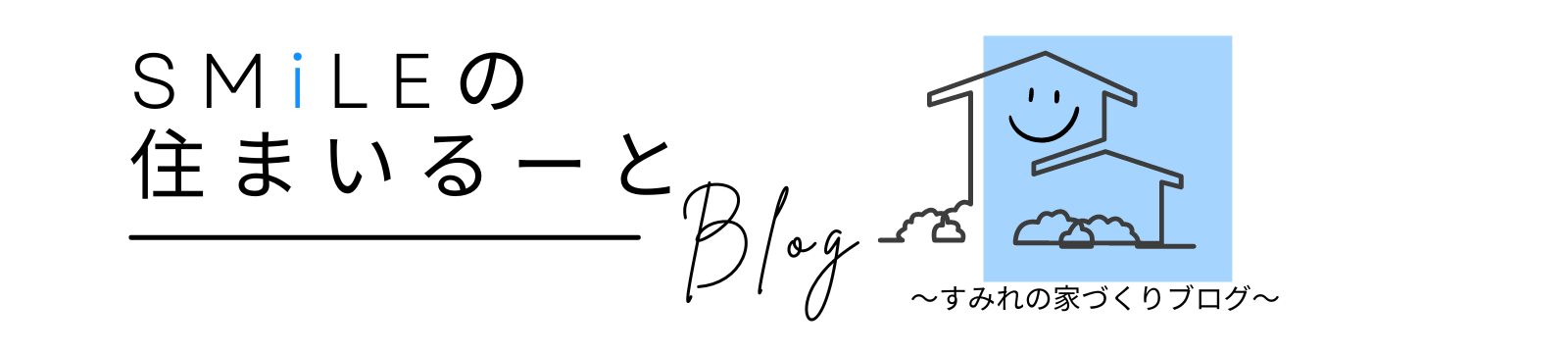
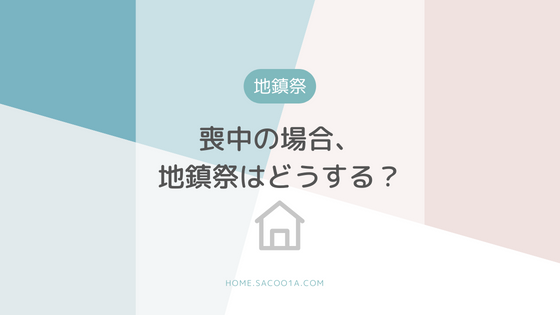





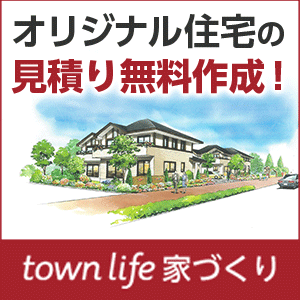


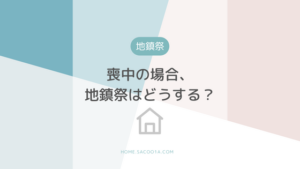
コメント